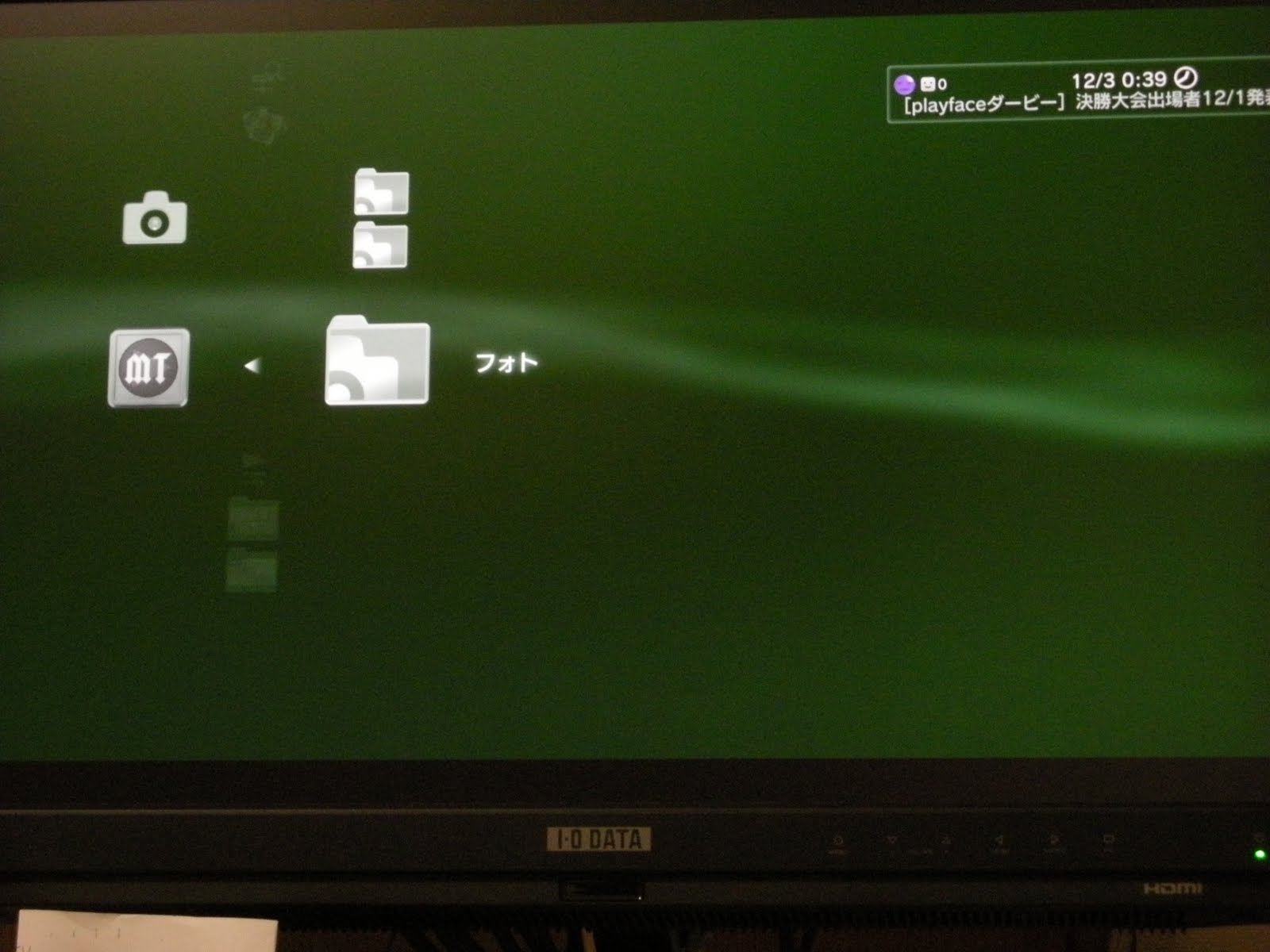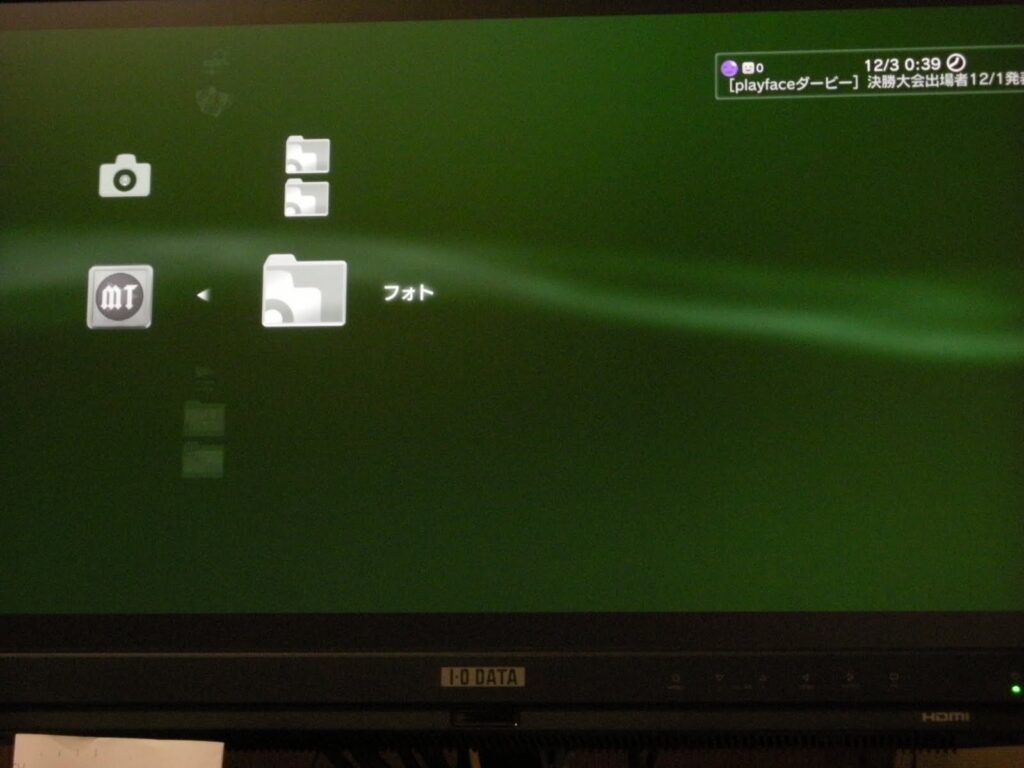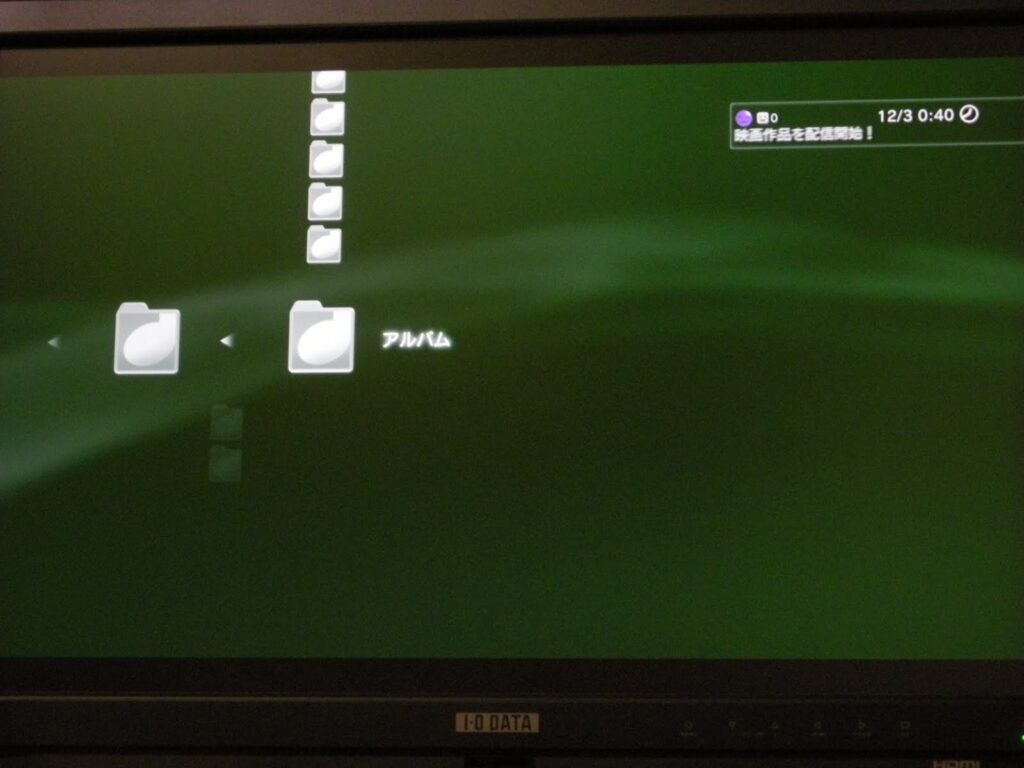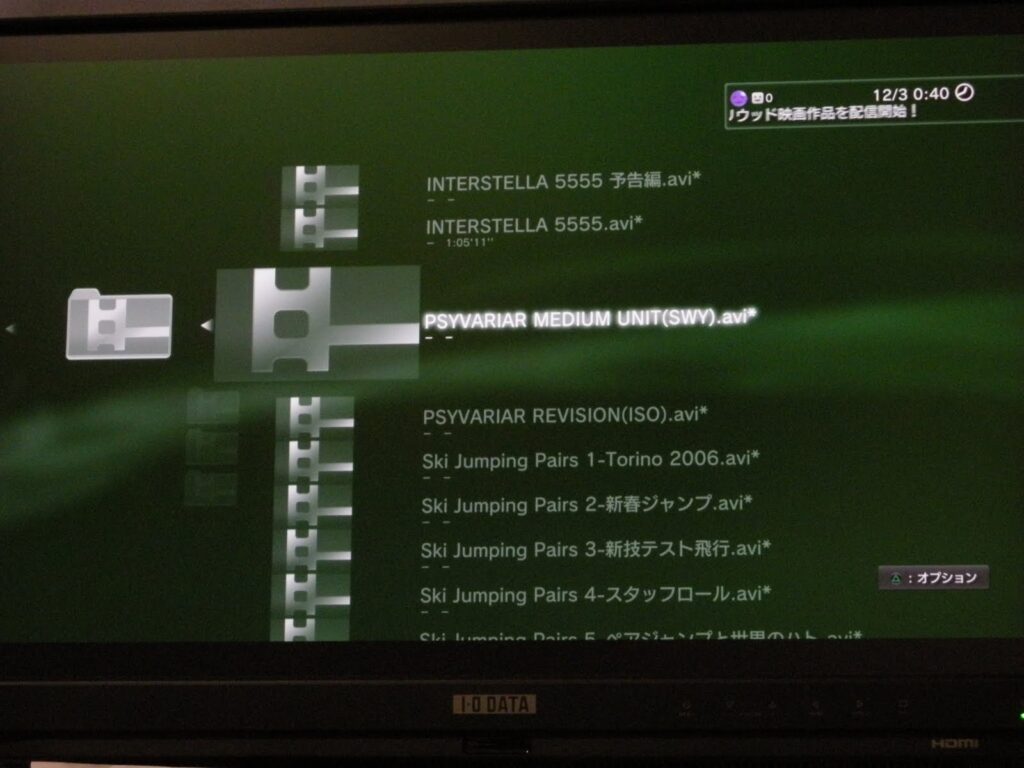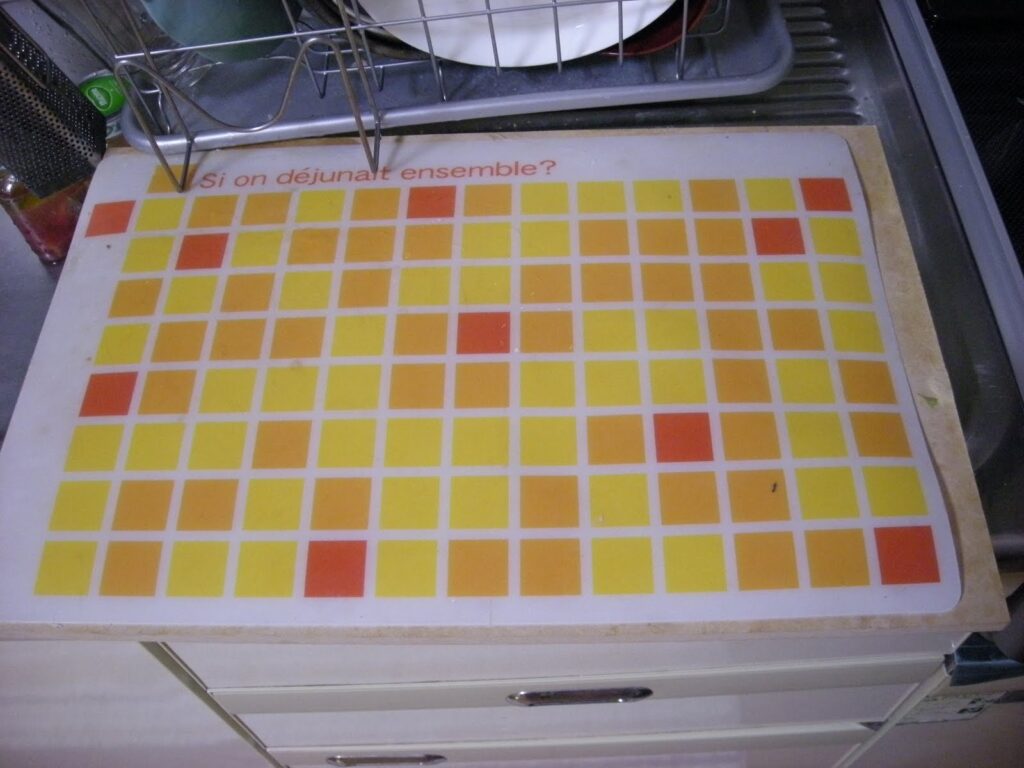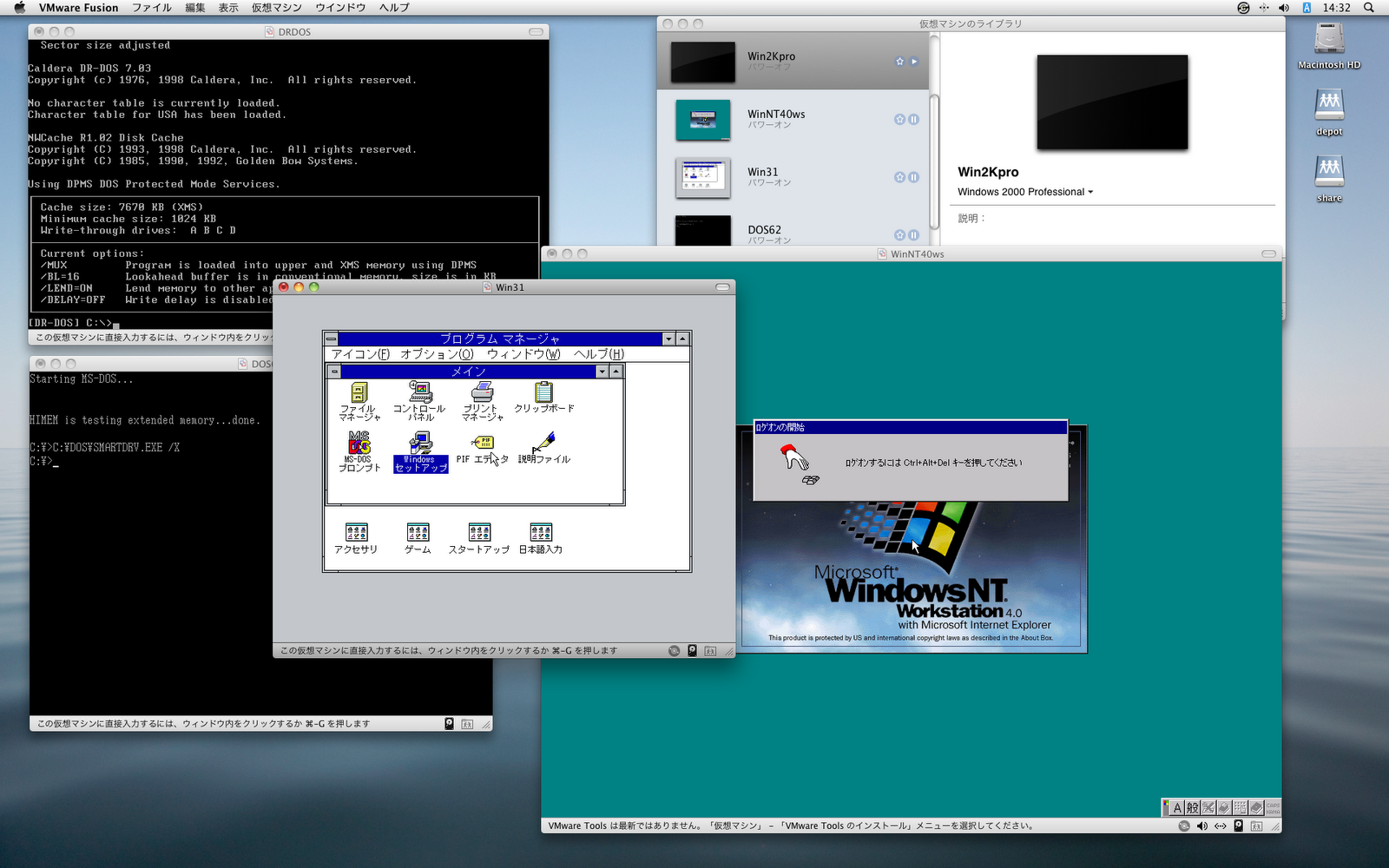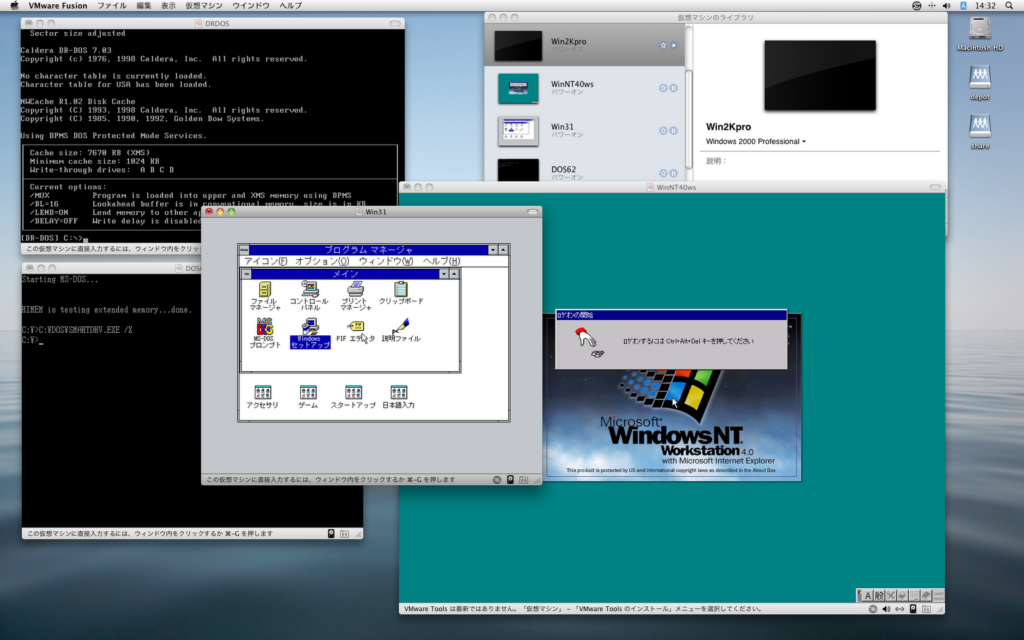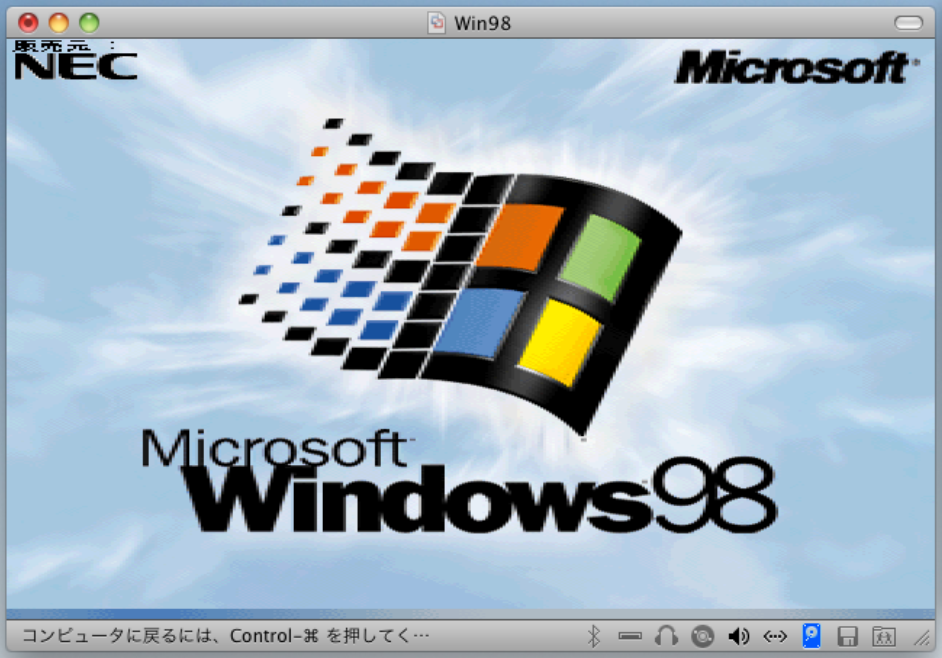本日の成果:SSDにした
あまり使ってないメインマシン(それはメインというのか?)のHDDをSSDに換装したよ。パラレルATA対応の速い奴を探したら、128GBのバカ高い奴しか見つからなかったので仕方なくそれを大枚はたいて入手したよ。うう、サーバ用途でもないのに128GBも使わないよう・・・。
そんでもって、長きにわたって愛用していたPartition MagicとDrive ImageのDOS版が、容量が大きすぎるせいか起動しない。バックアップ&リストアにはずっとコレを使ってきて、運用方法も確立してたのに・・・そしていつのまにか、販売もサポートも終了してる(涙)。しょうがないのでUSBメモリでUbuntu Linux立ち上げて、DriveImageと同じようにパーティションのバックアップ/リストアができるというPartImageというアプリを使うことにしました。それからPartition Magicの代わりにはGPartedを。コイツはPartition Magicより使いやすいな。あとはこれまで使ってたDrive Imageの*.pqiファイルを復元できるようにするためのコンバータとか互換ツールとかがあれば完結するのだだけど・・・入手できません。
あ、SSD速いです。昔ノートPCのHDD容量が20GBぐらいだった時代に、静かなHDDを求めていろいろなメーカーのを換装しまくった身としては、動作音がしないのもチョー嬉しい。電源のファンは相変わらず回ってますが。ストレージが速いので、こんどはCPUがボトルネックのように感じられてきました。なにせ5~6年前のシングルコアCeleronですもの。新しい奴買おうかな・・・。
あとで考えたら、SATA-PATA変換アダプタを使うという手もあったような気がする。
そしてそもそも、メインマシンはSATAの端子がついてた気がする。但し当時はSATA自体が登場したばかりで、EXPERIMENTALな位置付けだった気がする。(まけおしみ)